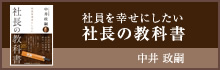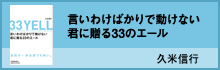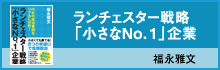-
ビジネスの視点2013年12月号
やっぱり、ピンチはチャンスだった! 危機を跳ね返す経営(津軽鉄道株式会社・社長 澤田長二郎氏)
肚を割って話せば必ずわかり合える

問題が起こったのは、赴任してから1年半ほど経ったころでした。ある早朝、白人の幹部から一報が入り、従業員のストライキを知らされました。採掘現場に急行すると、80名ほどいた従業員の姿が見えません。ストライキを起こしたのは先住民のアボリジニで、一部の白人が口にした差別発言に反発し、それへの抗議のため全員、居住区に引き揚げたのでした。
関係者から事情を聞くと、現場の険悪な雰囲気は容易に察しられました。アボリジニと白人の対立は一触即発と言える状況で、人種間の深刻な対立にもつながりかねません。私は、問題の根深さを直感しました。そして、アボリジニの不満が沸点に達するまで何もできなかった私自身の迂闊(うかつ)さを悔(く)いました。
しかし、私はこのとき、自分でも意外なほど落ち着いていたのをいまも覚えています。居住区に乗り込む覚悟を決めていたからです。相手の懐(ふところ)に飛び込んで、肚を割って話し合えば、必ずわかり合える。そう信じていましたから、身の危険を心配する白人幹部の忠告をありがたく聞き流し、私は単身、居住区に向かいました。われながら、よくそんな無鉄砲ができたものだと思いますが、精一杯の強がりだったのでしょう。私は、そこで働くたった1人の日本人でした。
結局、彼らが再び採掘現場に戻ってきてくれたのは、それから2週間後のことでした。しかし、その後も人権委員会の調査や職場討議などは続けられ、この問題のすべてが最終的に解決するまで、1年間ほどかかったでしょうか。会社そのものが空中分解しかねないピンチであったと思います。
ところが、これを契機(けいき)に社内の結束が強まったのですから、世の中はわかりません。日本人である私が緩衝材(かんしょうざい)になったのか、アボリジニと白人が議論を重ねるうち、相互の理解が深まったのです。雨降って地固まると言いますが、この騒動は会社にとって、まさに地固めのための慈雨(じう)でした。
商社マンとしての日常はハードで、その後も様々な経験をさせていただきましたが、97(平成9)年、三菱商事を定年退職した私は、関連会社で社長を務めた後、2004(平成16)年春、青森県五所川原(ごしょがわら)市に帰郷しました。悠々自適とはいかずとも、しばらくは懐かしい津軽の山野を眺めて、のんびり暮らすつもりでした。しかしながら、その年の秋には、旧知であった津軽鉄道の前社長から経営を引き継ぐことになるのですから、やはり因果な星の巡り合わせなのでしょう。しかも、就任早々、私は金策に走り回ることになります。